追記 2026年5月期第1四半期(2025年6月〜8月)のまとめ 一番下にあります。
ニュースを見ていると最近、半導体や量子コンピューターという言葉が良く飛び交ってる。でも投資をしているともう半導体は乗り遅れたのでは?量子コンピュータはまだできないのでは?という迷いが生まれてきてあまり手を出せない分野でした。そんな中で、これからの時代を牽引するテクノロジーの裏には、必ず“光”があるという話を目にしました。
光を精密に制御するレンズやミラー、ナノ単位で動く位置決めステージがなければ、最先端のチップも量子の世界も形にならないそうです。このテーマでPBR的に割安の銘柄を探した所、気になる銘柄があったので調べていこうと思います。
その銘柄とは光学インフラを手掛けているシグマ光機。研究室で定番の光学部品から、量子チップの調芯装置、半導体・医療分野まで、「光」を武器に成長を続ける企業です。
会社概要
ホームページを見るとシグマ光機株式会社は、1977年に埼玉県日高市で創業した光学機器メーカーです。レーザー関連の光学部品を出発点に、現在ではミラーやレンズといった要素部品から、位置決めステージや光学ユニット、さらにはシステム製品まで、幅広い光学ソリューションを手掛けています。
本社は埼玉県日高市にあり、東京(墨田区)にも第二オフィスを構えるほか、国内では大阪や九州に拠点を持っています。石川県の能登工場や技術センターでは、高精度な製造と研究開発が行われています。さらに「OptoSigma」のブランドで海外にも進出しており、中国・米国・フランスを拠点にグローバルに事業を展開しています。
同社は「光技術を通じて社会に貢献する」という経営理念をもとに、次世代産業を支える光学インフラ企業としての立ち位置を確立しようとしています。また、持続可能性や人材育成、透明性の高い経営を重視していることも特徴です。
「割安放置×鉄壁の財務基盤」シグマ光機の数字を読み解く
2021年から2025年の業績推移を見ていきます。
| 決算期 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 自己資本比率(%) | ROE(%) | PBR(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年5月期 | 8,766 | 11,500 | 80.0 | 5.96 | 0.88 |
| 2022年5月期 | 10,354 | 16,100 | 80.4 | 7.86 | 0.71 |
| 2023年5月期 | 11,367 | 16,900 | 78.7 | 9.19 | 0.66 |
| 2024年5月期 | 11,213 | 13,500 | 81.4 | 4.03 | 0.64 |
| 2025年5月期 | 11,580 | 12,700 | 86.9 | 5.58 | 0.55 |
数字から見える直近の推移は売上高・経常利益は2022年に大きく伸びた後、2023〜2025年は横ばい〜微減となっています。成長鈍化ではあるものの、極端な減退もなく基盤はしっかりしているという所です。
自己資本比率は右肩上がりです。2021~2025年でほとんど80%以上を維持しつつ、2025年には86.9%と非常に高く、安全性は強いです。しかし、資本が厚いため、ROEの改善には構造的な工夫が必要です。
ROE(自己資本利益率)は2023年がピーク(9.19%)から、2024年に4.03%へ急落し、2025年は5.58%へ回復しています。要因として経常利益は2024年に減少、2025年も小幅減となり、ROEに直接影響したもようです。利益の変動が大きい点はリスクにも見える一方、そこに機会も潜んでいます。
PBR(株価純資産倍率)は2025年8月時点で約0.59倍と多少見直されてきていますが、市場評価は依然として割安感があると言えます。
事業構成|要素部品からシステムまでワンストップ提供
概要でも触れたとおり、シグマ光機は“光”で課題を解決する光学ソリューション企業です。研究開発から生産現場まで、要素部品→ユニット→システムまで一貫対応し、国内最大手のレーザ用光学関連部品メーカーとして「ワンストップサービス」を掲げています。事業区分と主な商品を見ていきます。
事業区分と主な製品
1. 要素部品事業(売上比率84%)
- 光学素子・薄膜:レンズ・ミラー・プリズム等(1万品目超)、IBSコーティングによる超高反射ミラーなど。
- 光学基本機器:ホルダー、ベース、手動ステージ等(2千品目超)。
- モーション制御:自動ステージやコントローラ(200品目超)。
→ レーザの集光・反射・伝送・位置決め・制御の基盤を担い、研究から産業用途まで幅広く採用。
2. システム製品事業(売上比率16%)
- 干渉計、観察ユニット、モーションコントロールを組み合わせた測定・検査・評価・生産向けユニット。
- 微細加工や精密検査、生体分子観察など、応用先に合わせたカスタム展開が可能。
3. アプリケーションシステム
- レーザプロセシング装置(切断・刻印等)、光ファイバの調芯・溶接など実装現場対応。
- 医療・ヘルスケア領域では サーモメーター(OTLS-01) のような共同開発製品も展開。
成長分野ごとの注力製品
量子(量子計測・量子光学)
シグマ光機は、量子研究の世界でも欠かせない部品を提供しています。反射率99.999%という超高反射ミラーは、量子時計や精密計測に使われる「光をためる装置」の性能を引き上げる重要な部品です。
さらに、ナノメートル単位で動くステージ(物や光学部品を正確に動かすための装置)は、光の通り道を微調整する作業に活躍します。これらの装置を早期から導入し、研究機関・装置メーカーとの共同開発も行っています。
また、社内にある先端設備で、低損失・高耐久の光学パーツを量産できる点も強みで、「難しい光学装置を支える会社」という立ち位置を確立しています。
半導体(露光・検査・レーザ加工)
半導体の製造現場では、高出力のレーザを扱うため、長時間の照射にも耐える専用ミラーが必要です。シグマ光機の多層膜ミラーは、微細加工やマスク検査に必要であり、加えて、精密に動くステージや干渉計ユニットは、微細化が進む半導体工程の「測る・合わせる」を支えています。
部品単体だけでなく、ユニットやシステムとして提供できる点が評価されており、今後注力していく方針です。
医療・バイオ
医療分野では、血中酸素と体温を同時に測れる「オキサモメーター」が代表的です。これは医療機器として認証も受けており、光技術を健康管理に活かした例です。また、透明なサンプルや生体分子を観察する光学ユニットも展開しており、研究室から病院まで幅広く役立っています。「研究の成果を実用に結びつける」橋渡し役を果たすのが特徴です。
通信(光通信デバイス)
通信の分野では、光ファイバをナノレベルで位置合わせできる「多軸調芯システム」が強みで販路拡大の方針です。光素子や導波路を正確に組み立てる工程で使われ、通信デバイスの生産に欠かせません。さらに、観察ユニットやNFP観察キットは検査の効率化に貢献しており、5G/6G通信デバイスの量産やデータセンター需要の拡大を追い風に、シグマ光機の光学ユニットは成長市場での存在感を高めています。
量子・半導体・通信の分野では「ちょっとのズレ」が大きな誤差につながるので、高精度で安定して動かせるステージは不可欠です。シグマ光機の強みは、このステージを 光学素子や観察ユニットと一緒に提供できることで互換性・調達効率・カスタマイズ対応・信頼性の点に強みがあります。
「PBR0.5倍 vs PBR4倍」シグマ光機と競合の明暗
国内で近い分野である光学系、フォトニクス分野で上場しているサンテックHDと精工技研を見ていきます。売上高ベースでは二倍程度の開きがありますが、圧倒的な開きはないので同分野の競合として比較しました。
(期末がバラつくため、最新通期:シグマ光機=2025年5月期、サンテックHD=2025年3月期、精工技研=2025年3月期で統一比較しています。)
| 企業 | 期末 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 自己資本比率 | ROE | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シグマ光機(7713) | 2025/05 | 11,580 | 1,269 | 86.9% | 6.0% | 0.56倍 |
| サンテックHD(6777) | 2025/03 | 24,027 | 7,888 | 72.6% | 24.9% | 4.05倍 |
| 精工技研(6834) | 2025/03 | 19,983 | 2,979 | 82.9% | 8.6% | 2.52倍 |
フォトニクス/光学関連の上場企業を比較すると、売上規模ではサンテックHD(約240億円)>精工技研(約200億円)>シグマ光機(約116億円)という順序になります。いずれも同じ光学分野に属しますが、事業ミックスには違いが大きく、サンテックは光通信向け測定器・光部品に強みを持ち、海外需要を取り込みやすい体質。一方のシグマ光機は、要素部品を中心にユニットやシステムへと展開している構造です。
数字から見えてくる収益性と市場評価を比べると、数字の違いは明確です。
- サンテックHD:ROE約25%・PBR約4倍 → 高収益企業として市場から高く評価される典型例。
- 精工技研:ROE約8.6%・PBR約2.5倍 → 収益性・評価ともに中位。
- シグマ光機:ROE約6%・PBR約0.56倍 → 安全性は極めて高いが、割安に放置されがち。
ここでは「高ROE=高PBR」という教科書通りの関係がそのまま表れており、資本効率とユニット等の高粗利製品比率の差が株価評価に直結しています。
サンテックは光通信・測定器といった外需ドライバーが中心で、景気敏感かつ高利益率のビジネスに寄せていますが、シグマ光機は要素部品の比率が高く、システムやユニット比率が低いため、粗利水準は競合に比べて伸びにくい。
逆説的に見ていくと、シグマ光機には見直し余地があります。ユニット/装置比率の上昇により粗利率が改善し、ROEの底上げにつながる。米欧市場における半導体・医療・防衛分野の受注が増えることで、成長ストーリーを明確化できる。自己株買いやROE目標の明示といった施策により、資本効率を高め市場へのメッセージを強められる。などが起きれば評価の見直しが起こることは十分に考えられます。
「要素部品から脱却せよ」中期経営計画が描く未来
1. 中期経営計画の基本方針
シグマ光機は、中期経営計画において「量子・半導体・医療・通信」を次世代の成長市場と位置づけ、光学素子からユニット、システムまでを提供するワンストップソリューション企業としての地位強化を掲げています。
その実現に向けて、以下の3つの柱を明確化しています。
- ① 生産体制の拡充と高付加価値化
- ② グローバル販売ネットワークの強化
- ③ 財務基盤を活かした積極投資と資本効率改善
2.中期経営計画から見えてくる成長戦略
設備投資と生産体制の拡充
①に対応して中期計画の実行力を支えるのが、2023~2024年にかけての相次ぐ投資です。
- 技術センター(2023年7月):新工場棟2棟を増設し、研究開発・量産の両輪を強化。
- 能登工場(2024年10月):既存棟をリノベーションし「オプト・メカ・ファクトリー」を整備。光学素子から光学システムまで一貫対応する生産ラインを構築。
- BCP強化:能登地震からの早期復旧、複数拠点によるリスク分散で安定供給を確保。
→ 設備増強により「高精度非球面レンズ」「高NA対物レンズ」といった高付加価値製品を投入し、売上単価と粗利率の改善を図るシナリオです。
成長分野への積極対応
中期経営計画では、量子技術、半導体、医療・ライフサイエンス、通信の分野を成長ドライバーと位置付けています。
→「要素部品に依存しない収益体質」への転換を明確に打ち出しており、システム・ユニット比率の上昇を通じて収益力を強化する戦略です。
グローバル販売ネットワークの強化
- 欧州拠点新設(2023〜2024年):OptoSigmaブランドを浸透させ、現地対応を強化。
- EC販売拡充:欧州では受注の約15%がEC経由に到達。研究機関や中小顧客を直接取り込むチャネルとして重要性が増大。
- 米国・アジア子会社の拡充により、グローバルシェア拡大の土台を整備。
→ 中期的には「国内研究機関向けの安定需要」から「海外の成長市場」に軸足を移し、売上の海外比率を高めていく方針です。
光学(フォトニクス)市場の成長性と注目分野
1. 市場全体の見通し
光学(フォトニクス)は、光を制御・利用する技術全般を指し、レンズやミラーといった部品から、レーザ加工装置、医療診断機器まで幅広い領域をカバーしています。
世界全体の市場はすでに数百兆円規模に達しており、今後も年率4〜5%前後の安定した成長が見込まれています。背景にあるのは、半導体の微細化、通信インフラの高度化、医療需要の拡大といった構造的な成長要因です。つまり「光を使わなければ成立しない産業」が増えており、これが市場全体の底堅い拡大を支えています。
2. 分野ごとの成長トレンド
通信・データセンター
生成AIの普及でデータ処理量が爆発的に増加し、800G・1.6Tといった次世代光通信モジュールが必須に。シリコンフォトニクスや高精度光学部品が不可欠で、今後も高成長が見込まれる分野です。
産業分野(半導体・EV・精密加工)
半導体の微細化やEV電池の製造では、レーザ加工や光学検査が欠かせません。安定した需要が続き、堅実に成長する領域と見られます。
医療・ライフサイエンス
内視鏡やOCT、バイオイメージングなどの診断技術は高齢化や早期診断ニーズを背景に拡大中。研究から臨床応用への展開も追い風となっています。
量子技術
量子コンピュータや通信には超高反射ミラーやナノ精度ステージが必須。まだ小規模ですが、国家プロジェクトの後押しもあり高成長が期待される分野です。
自動車・XR
自動運転用LiDARやAR/VR光学デバイスも市場拡大が続いています。ただし製品化まで時間がかかり、価格競争も激しい点には注意が必要です。
「AI × 光学」が生み出す新しい需要
1. なぜAIと光学は結びつくのか
人工知能(AI)は膨大なデータを処理して学習を進める技術です。そのためには、データをいかに早く効率よくやり取りできるかが決定的に重要になり、ここで活躍するのが光学です。サーバーをつなぐ光ファイバ、その中を通る光を制御するレンズやミラー、信号の損失を防ぐための薄膜コーティング、そして次世代技術として期待されるシリコンフォトニクス。いずれもAIが動くための裏方であり、AIと光学は切っても切れない関係にあるのです。
2. データセンターでの具体的な広がり
ChatGPTのような生成AIを動かす巨大なデータセンターでは、数万台規模のサーバーが常時稼働しています。これらがやり取りするデータ量は膨大で、今や従来の400G通信では足りず、800G、さらに1.6Tへと進化が求められています。その進化を実現するのが光学部品です。シリコンフォトニクスによってデータの伝送効率を飛躍的に高め、低損失コーティングで熱による信号劣化を防ぐことができます。AIの進化はすなわち光学部品の需要拡大につながっており、ここ数年の市場成長の主役となっています。
3. スマート工場におけるAIと光学の融合
AIと光学の結びつきはデータセンターにとどまりません。製造現場、いわゆるスマート工場でも広がっています。検査ラインでは高解像度カメラで製品を撮影し、その映像をAIが解析して不良品を即座に判定します。ロボット制御では光学センサーからの情報をAIが処理し、精密な組み立て作業を実現します。さらに、安全管理ではAIが人や物の動きを光学的に検知し、事故を未然に防ぎます。ここでも数多くの光学センサーやカメラが導入され、AIと光学が一体となって製造業を変革しています。
4. 医療、自動運転、そして未来へ
AIと光学の組み合わせは、今後さらに幅広い分野へと広がります。医療の現場では、内視鏡や眼科診断装置(OCT)から得られた映像をAIが解析し、病気の早期発見や診断精度の向上に役立てています。自動運転分野では、AIがLiDAR(レーザーレーダー)からの光学データを処理することで、障害物や歩行者を瞬時に検出し、安全な走行を実現します。将来的には量子コンピュータと光学素子が組み合わさり、AIの処理能力を飛躍的に高めるといった可能性も期待されています。
5. まとめ
光学市場は、半導体・通信・医療といった既存分野の堅実な成長に加え、AIや量子といった新技術が追い風となり、今後も拡大が続くことが予想されます。特に「AI × 光学」の関係は、データセンターやスマート工場をはじめ幅広い産業で需要を押し上げており、ここ数年の最大のドライバーになるでしょう。
シグマ光機は、要素部品からシステムまでを手掛けるワンストップの光学ソリューション企業であり、量子や半導体といった成長分野に直接関わる製品を持っています。財務基盤の強さやグローバル展開力を背景に、割安に放置されている株価が再評価される可能性も高いと言えます。
一方で、要素部品依存からの脱却が進まなければ株価は割安に放置され続ける可能性もあります。投資判断では、この両面を意識することが欠かせません。
光学という視点で未来を考えると、まだ掘り出し物の余地が残されているのかもしれませんね。
追記 2026年5月期第1四半期(2025年6月〜8月)のまとめ
追記です。2026年5月期第1四半期(2025年6月〜8月)の決算では、シグマ光機の業績はやや軟調なスタートとなりました。まずは前年同期との比較を表で整理します。
| 指標 | 2026年5月期1Q | 2025年5月期1Q | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 25億500万円 | 26億5,495万円 | ▲5.6% |
| 営業利益 | 1億5,219万円 | 2億1,271万円 | ▲28.5% |
| 経常利益 | 1億8,939万円 | 2億2,816万円 | ▲17.0% |
| 四半期純利益(親会社株主) | 1億817万円 | 1億4,579万円 | ▲25.6% |
| 1株当たり四半期純利益 | 15.31円 | 20.58円 | ― |
粗利率は36.5%と小幅に改善しましたが、人件費や減価償却費、外注加工費などの増加が利益を圧迫し、営業利益率は前年の8.0%から6.1%に低下しています。
セグメント別では、主力の要素部品事業が国内エレクトロニクス向けで弱含みとなり、光学素子や薄膜製品が軟調に推移しました。
一方で、システム製品事業は電子部品・半導体関連の需要回復や医療分野での大型案件の納品が寄与し、前年の赤字から黒字へ転換しました。地域別にみると、アジア向け需要は中国を中心に持ち直しの動きが見られる一方、国内需要の戻りはまだ鈍い印象です。
財務体質は引き続き堅固で、総資産は199億円、純資産は177億円、自己資本比率は88.2%と高水準を維持しています。現金や有価証券の減少により流動資産はやや縮小しましたが、借入金は少なく、安定した財務基盤が続いています。
会社側は通期業績予想を据え置き、売上高116億9,500万円(前期比+1.0%)、営業利益12億2,000万円(+7.9%)、経常利益13億2,000万円(+4.0%)、純利益8億8,500万円(▲10.2%)を見込んでいます。配当も年間42円(中間・期末各21円)を維持する方針です。
今回の決算は、一時的なコスト増と需要の偏りによる減益が目立ちましたが、粗利率の維持やセグメントごとの持ち直し傾向を見ると、構造的な悪化ではなく助走期間と捉えることもできます。株価は決算後に下落しましたが、自己資本比率88%・PBR 0.6倍台という財務安定性と割安感を踏まえると、下期の進捗次第で再び評価が戻る余地もあるかもしれません。
会社の通期据え置きは、助走期間だったのか、本当に業績が悪化している始まりなのか、次の四半期決算も引き続き監視していきましょう。
参考文献・出典
- シグマ光機株式会社「有価証券報告書(2025年5月期)」
https://www.optosigma.co.jp/jp/ir/ (公式IRページ) - サンテックHD「決算短信(2025年3月期)」
https://www.santec-holdings.co.jp/ir/ - 精工技研「有価証券報告書(2025年3月期)」
https://www.seikogiken.co.jp/ir/ - 経済産業省「フォトニクス産業に関する調査報告書」
https://www.meti.go.jp/

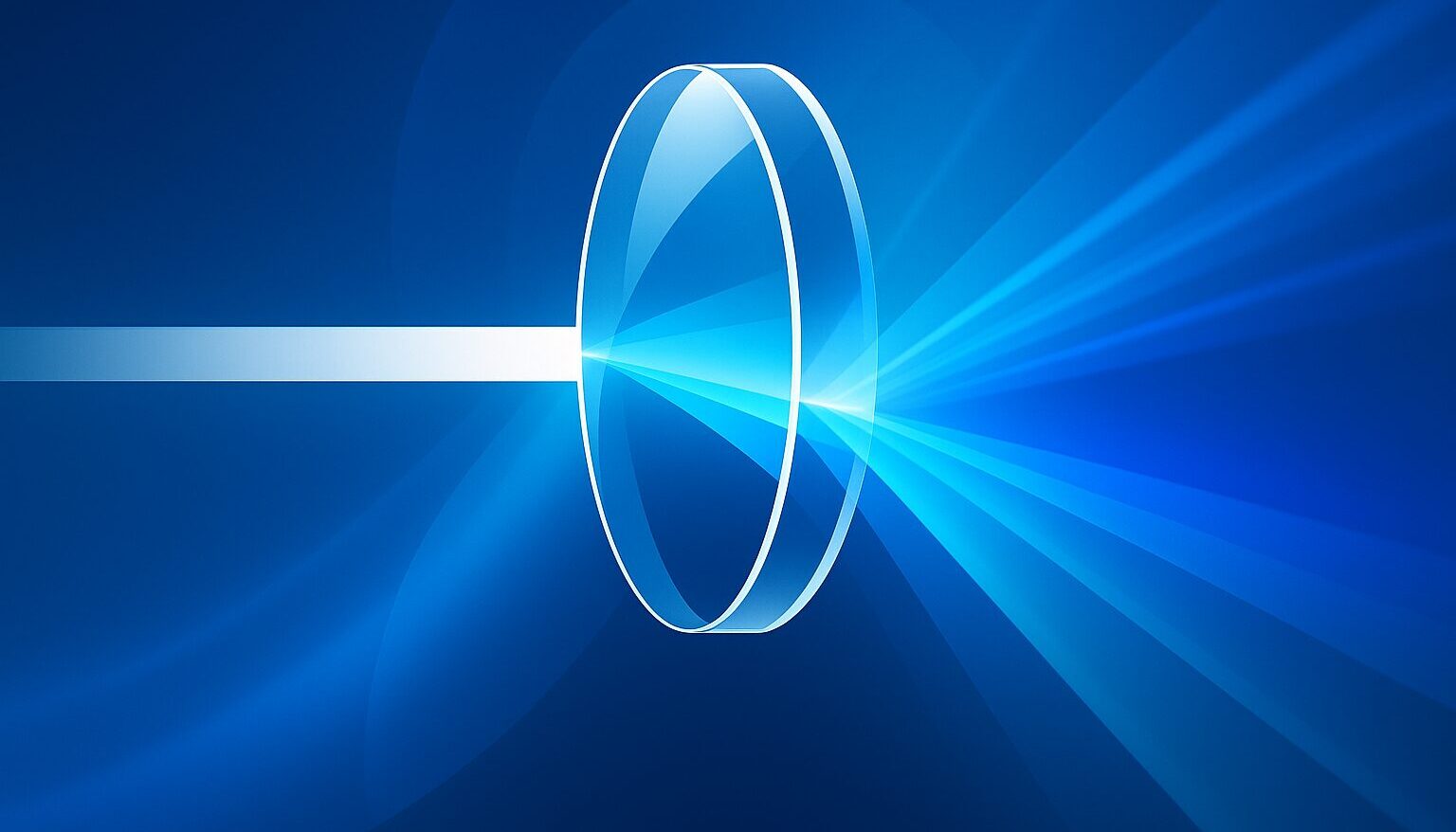
コメント